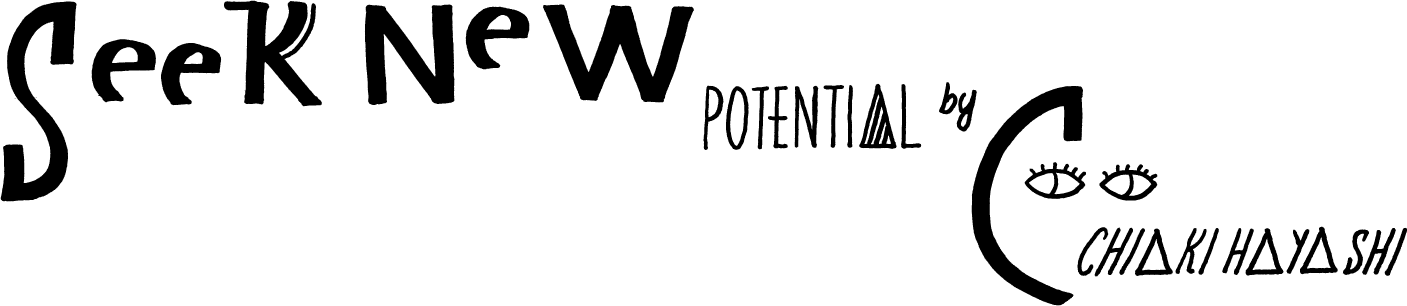ダニエル・ビュレン《回廊の中で:この場所のための4つの虹 ー KENPOKU ART 2016のために》
9月17日に茨城県北芸術祭が開幕して、早1ヶ月。参加アーティストは85組、100点以上の作品が、東京23区の2.7倍もある県北エリアに設置されたスケールの大きな芸術祭だ。
広すぎて迷子にならないだろうか。水郡線の終電が早すぎて帰れなくならないだろうか。そもそも芸術祭を楽しんでもらえるだろうか。開幕前の心配は、嬉しいことに杞憂に終わった。目標だった来場者数30万人は、わずか1ヶ月で達成。すこぶる評判もいい。
オンラインで #KENPOKU #茨城県北芸術祭 タグをチェックすると、アート好きだけでなく、地元の人たちが素直に楽しんでいる様子が伝わってくる。実際、会場にいるとおばちゃんたちがグループで来て、「あれ〜!あんたこれ、すごいわよ」「ちょっとちょっと、これ見て」なんて子供のようにはしゃいでいる光景をよく目にする。メディアの人たちも、泊りがけの取材で愛情のこもった記事に仕上げてくれた。
NAVERまとめ「本気を出した茨城県。茨城県北芸術祭が素敵すぎる。」ケンポクに行ってきました! 『KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭』リポート。注目の国際芸術祭『KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭』リポート<山側編>
この芸術祭の企画に参画したのは約2年前。単にアート好きとして楽しむだけだった「芸術祭」に、主体的に関われることでわかった面白さ、発見、可能性。この貴重な体験を、芸術祭の可能性も含めて、少しまとめてみることにする。
原 高史《サインズ オブ メモリー2016:鯨ケ丘のピンクの窓》
日本には芸術祭が多すぎる?!
まず、芸術祭というと「またか」という反応が返ってくることが多い。確かに、いまや日本中で芸術祭が開催されている。作品をつくるアーティストも大変だが、観てまわる側だって大変だ。アートライターの友人は「もうヤケだ。時間とお金の許す限り、見てまわってやる」と開き直っていた。
ブームに便乗しただけの取り組みは、長くは続かないだろう。私も初めて茨城県の候補エリアを視察するときは、「ここで芸術祭を開催する意味があるのかな」と半信半疑だった。でも一度、県北エリアに足を踏み入れてみると、知らなかった茨城の奇妙な歴史や、力強い自然が生み出す景色に驚き、魅了された。そして、これは多くの人に知ってもらう価値のある物語だと強く感じた(その理由はあとで詳しく語るとして)。
同じように、芸術祭の主催者は、その土地の歴史や自然、継承されてきた文化に魅了され、多くの人にそれを伝えてみたいと思って始めるのかもしれないなあ。そんな風に感じていたときに、偶然、芸術祭を手がけるディレクターのトークイベントがあった。そこで北川フラムさんと南條史生さんが、面白いコメントをしていた。
北川さん曰く、「芸術祭が多いからって、何の問題があるんだい。アートはさ、『つまらない』ってことはあっても、害はもたらさないよ。ちょっと増えたからと文句を言っている暇があったら、僕はアートの可能性を追求したい」と。
また、南條さんはこうも言っていた。「日本には古くから祭りの文化がある。春祭、夏祭、秋祭。日本中、いたる所で祭が開催されていて、地域をつなぐ役割を担っている。隣町で祭をやるからこの町でやってはいけないというルールはない。芸術祭も、同じではないか。文字どおり、現代版の『祭』として、地域のコミュニティを作り、土地の価値を継承する役割を担えるのではないか」と。二人ともさすが説得力があるなあ、と感心してしまった。
見よう見まねの活動では意味がないけれど、芸術祭が多いという理由だけで否定するのも、これもまた乱暴。芸術祭は、忘れられていた土地、そこで暮らす人の生き様に目を向け、アーティストの新鮮な眼差しを通じて、価値を再発見する役割を担うことができる。それが、訪れた人に思わず「わお!」と驚きの声をあげさせる新鮮な体験となり、その土地で暮らす人たちの活力にもなりうる。色々な可能性をひめた、壮大な社会実験。それが私の芸術祭に対する認識だ。
ピーター・フェルメーシュ《Untitled (kenpoku)》