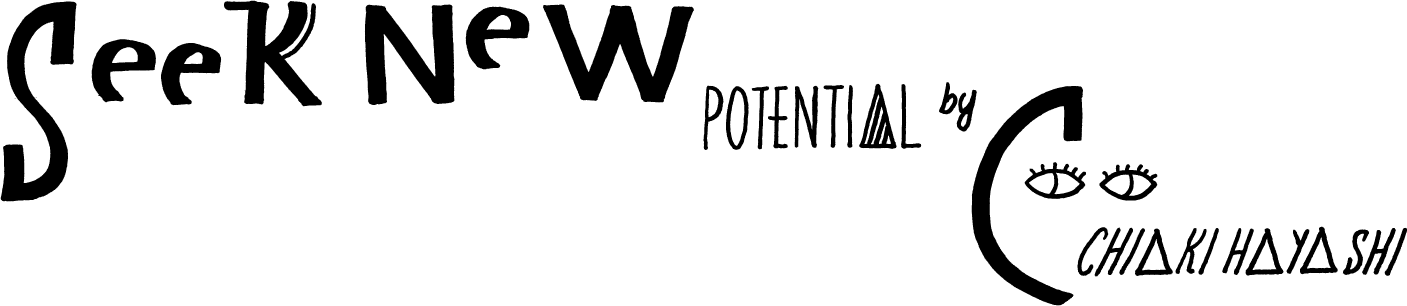アート好きは今夏、ヨーロッパを目指す。
なんせ、2年に一度の「ヴェネチアビエンナーレ」と、5年に一度の「ドクメンタ」、10年に一度の「ミュンスター彫刻プロジェクト」という大規模な芸術祭が同時開催されるのだ。こんなに揃うのは何年振りなんだろう。冷静に考えるとミュンスター彫刻プロジェクト開催年は、毎回この3つが揃うことに気づくのだけど(笑)、それでも大当たりの年であることには違いない。
中でもミュンスター彫刻プロジェクトは印象深く、その割に日本語で手に入る情報が少ないので、これから観に行く人のために見どころをまとめておくことにした。
『ミュンスター彫刻プロジェクト』
- 開催は2017年6月10日から10月1日まで
- ドイツ北西部の都市ミュンスターにて開催
- 1977年創設、10年に一度のペース
- 無料で見ることができるパブリックな展覧会
- 4回目の今回はアーティスト35組が参加
- 日本からは田中功起と荒川医(あらかわえい)の2名
「スカルプチュア(彫刻)」という言葉から、なんとなくブロンズ像で伝統的なものを想像していたが、行ってみるといい意味で大きく期待が裏切られた。それは、日本でいう「芸術祭」のような仕掛けだった。公園の芝生、大学の広場、運河、川辺など、土地がもともと持っている景色に、建築的なものや、インスタレーション的な作品がインストールされて、特別な体験を生み出している。
アートが加わるだけで、ずっと変わらずにある芝生の青さが、愛おしくなる。日常のありふれた景色が、作品によってリフレーミングされ、一気に非日常の世界に連れて行かれてしまう。これぞ、アートの力だなと感心してしまった。
また絵画作品と異なり、自然にインストールされる彫刻作品の多くは、見る側の「参加」によって作品が生み出される。単なる解釈の問題だけでなく、観る位置、観る時間、観る角度、本人の視力などの条件により、作品体験が異なるのも面白い。オラファー・エリアソンの言う「インクルーシブなアート」というものなのかな。
主催しているミュンスター市は、自転車での回遊を推奨していて、おじいさんやおばあさん、子供、観光客、みんながぐるぐる自転車で作品を見てまわる様子は、なんとも微笑ましい。堅苦しいアート論は不要で、彼らの笑顔が、主催者やアーティストを「やってよかった!」と腹落ちさせてくれるのだ。今でこそ、50万人近い人が訪れるミュンスター彫刻プロジェクトだが、始めた時は住民が大反対だったという。新しいことを始めるときに、なかなか理解が得られないのは、世界共通ということなのか。
そんなミュンスターの芸術祭。今年の話題作品は、何といってもグレゴール・シュナイダー、アイシャ・エルクマン、ピエール・ユイグの3作品だろう。
まず、運河をジャブジャブ渡らせてしまうのが、エルクマンの『On Water』。ベルリン在住のエルクマンは、水面下に金網で作られた橋で、今は使われていない運河の両岸を繋いだ。現代人が一直線に、ただ列になって水面を歩く姿は巡礼の儀式のようであり、民族大移動のようである。あるいは、移民がメタファーなのかもしれない。でも大きく違うのは、渡っているみんなが満面の笑みを浮かべているところだ。ロープもない。監視員が声を上げるでもない。落ちるも、泳ぐも、個人責任というオペレーションは、さすが個人主義が成熟しているヨーロッパならでは。水辺の活用という点でも、いいインスピレーションになった。
次に列になっていたのは、フランス出身アーティスト、ピエール・ユイグの作品。こちらは使われなくなったアイスリンクが舞台だ。彼は大胆にリンクを切断。出現した景色はまるで現代の廃墟。そこに大きな蜂の巣を作り、天井を開閉させて蜂の生態を保つ。人間が作ったものはいずれ廃墟になっても、自然はたくましく、全てを生態系に戻していくという物語が浮かび上がり、文明へのアンチテーゼのようにも見える。
最もミステリアスで長い列ができていたのは、グレゴール・シュナイダーだ。これから観る人のために細かい説明はしない。これこそ、体験した人にしかわからない作品だ。でも過去の代表作と同様、それは壁の外に壁があり、部屋の中に部屋があるかのように、観る人は不気味な空間を彷徨うことになる。
え?
なぜ?
ここはどこ?
何が起こっているの?
作品が生み出す「異空間」に身を置きながら、心臓がドキドキすることは間違いない。朝10時オープンにもかかわらず9時過ぎこのように長蛇の列。週末には1時間以上、待つこと必至だ。
目当ての3作品をコンプリートしたら、次に興味が湧くのが日本人アーティストの作品。この芸術祭で初めて知ったのが荒川さん。彼の作品は、中心地からほどよく離れた川沿いの草原を背景に、LEDのキャンバスで土地にまつわる物語を表現していた。田中功起さんはいつものように、ワークショップ形式で生まれる映像作品。深いダイアローグからしか生まれない本音のぶつかり合いを通じ、移民、多様性の受け入れ、その周辺の複雑な感情を浮き彫りにしていた。
もう一つ、ミュンスター彫刻プロジェクトで見逃せないのが過去に作られて恒久展示になっている作品たちだ。豪華なアーティストの名前が、ずらっと並んでいる。とても1日で見てまわれる量ではないので、ダニエル・ビュレン、ブルース・ナウマン、イリヤ・カバコフあたりを目標に定め、街中を回ってきた。
大学キャンバスに巨大な四角錐を作り出したのは、アメリカ人アーティストのブルース・ナウマン。直島にあるネオン管の作品「100生きて死ね/100 Live and Die」が有名だが、ミュンスターで対面したのは、なんとも潔い建築作品だ。1977年、第一回目開催時にナウマンが提案したけれど許可が降りず、30年の歳月を経て実現した作品だという。25 x 25メートルの正方形が、緩やかに地中へと潜っていく。対角線上を歩いていると、なぜか背筋がピンと伸びてくる。どこへ向かうのか。何に向かっているのか。そんな問いが生まれてくるのが不思議だ。
カバコフも、さすが。見上げると、雲の上に、青空の中に、繊細なテキストが浮かび上がってくる。なんと書いているのかわかれば、もっと面白いのに。その他にも、まるでスタンプラリーのように、街中に散りばめられた作品を見つけて歩くのは、今年ならではの、とっておきの夏の過ごし方かもしれない。



芸術祭が多すぎるのではなんてコメントも聞くけれど、そもそも「祭り」は至るところで開かれてきた。季節にあわせ、土地の文化を継承しながら、人と人の繋がりを育んできた。芸術祭も、現代の「祭り」のあり方のひとつ。その土地に行ってみたくなる面白い仕掛け。何より、アートがきっかけで、その土地の文化や人に触れ、ファンになる。なんとも素敵な流れではないか、と納得してしまったミュンスターの旅であった。