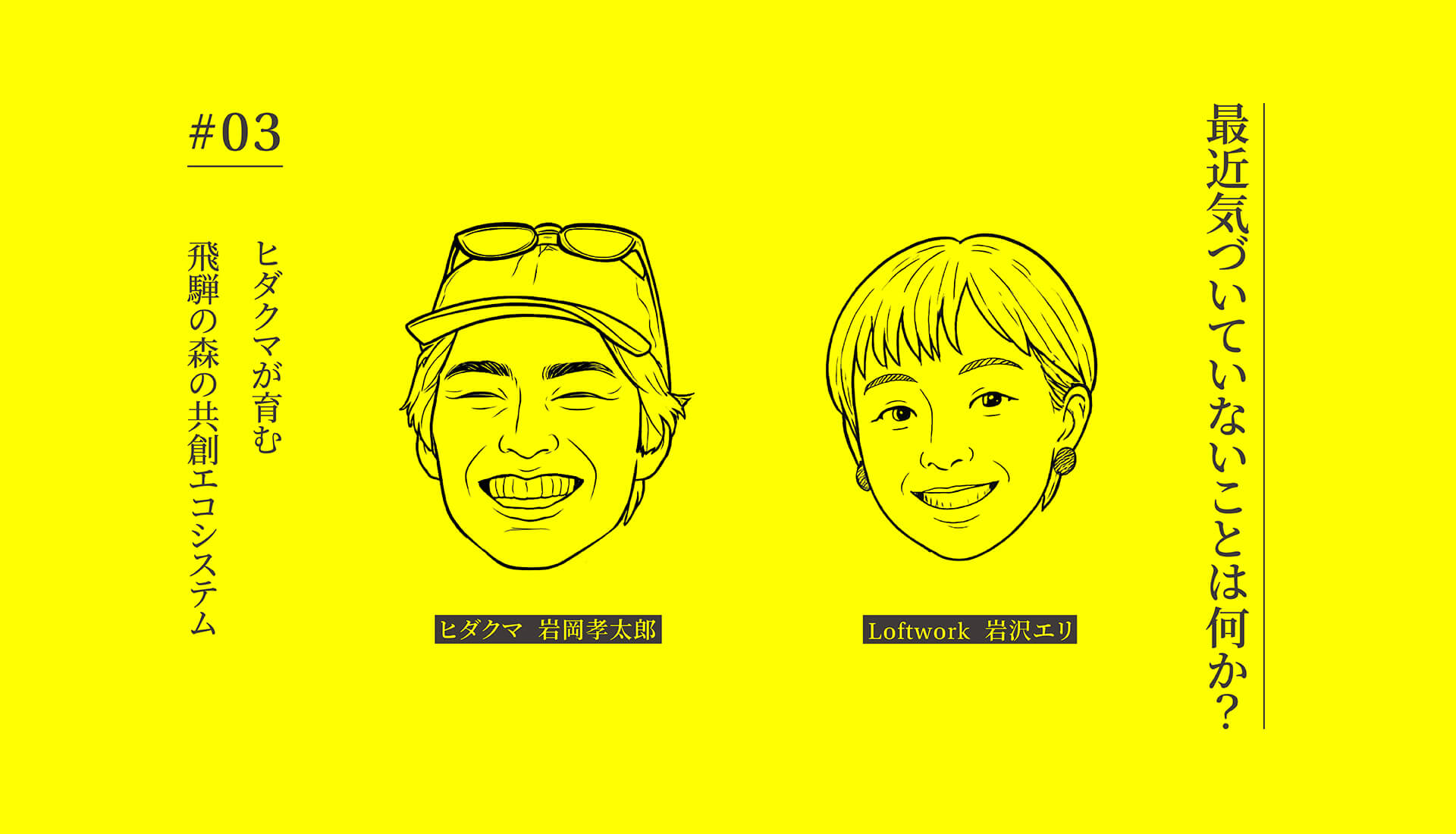
【連載】最近気づいていないことは何か?
#03|ヒダクマが育む飛騨の森の共創エコシステム
森の価値を探求する「味方」を増やし、多様な「見方」から芽生えるイノベーション
多元世界。言い換えれば、正解や価値が一つのものさしでは図ることができない世界があるということ。この言葉が、ビジネスの世界でも注目され始めているのは、誰しもが収益性や効率性といったものさし以外の別の可能性をたしかに感じ取っているからではないでしょうか。
岐阜・飛騨の山あいに目を向けると、都市とは違うリズムで生まれている営み、新たな兆しがあります。過度な計画性を手放し、偶発性に開かれる。小さな種を「待つ」ように育てる。そこに新しいイノベーションのあり方を垣間見ることができるかもしれません。「最近気づいていないことは何か? ― 多元世界探訪記」第3回では、ロフトワークが飛騨市役所と、地域の森林・林業を起点とした事業を創出するトビムシと共に立ち上げた森のクリエイティブカンパニー「株式会社飛騨の森でクマは踊る(通称:ヒダクマ)」を訪ね、森の「雑木」から立ち上がる新しい産業と文化を見つめます。
そこで目にしたのは、経済合理性からこぼれ落ちた広葉樹の森を多様なプレイヤーにひらき、森の可能性を探求する「味方」と「見方」を増やしながら、自然のようにゆっくりとイノベーションを育んでいく、森のように有機的で共創的な営みでした。

「経済合理性」からこぼれ落ちた森。辺境から芽生えるイノベーション

「飛騨の広葉樹って、面白いんですよ。曲がっていたり、節があったり。そういう『個性』がある。工業製品の材料としては扱いづらいけど、その個性を生かして価値をつけられないか? その問いが、ヒダクマが創業したきっかけでした」
そう語るのは、ヒダクマ創業初期メンバーの一人で、今回の「多元世界探訪記」の案内人である岩岡孝太郎さん。ヒダクマは、95%がチップ用として地域外に安価に流出していた飛騨の広葉樹に、クリエイティブの力で新たな可能性を吹き込み続けている森林ベンチャーです。
戦後の林業が「規格化」と「効率化」によって市場を拡大してきたのだとすれば、ヒダクマは「個性化」と「付加価値化」によって新たな市場を創り出し続けています。そして、その試みは、森林業界だけでなく、ビジネス全般に行き渡る、「拡大」、「効率性」といった大量生産・大量消費的な資本主義へのオルタナティブとしての可能性をも秘めています。

岩岡さんがまず最初に案内してくれたのが、そんなオルタナティブを体現したヒダクマの新たな拠点、「森の端(もりのは)オフィス」です。これまで「広葉樹は建材にならない」とされてきた常識を覆し、広葉樹をふんだんに使った三角構造が印象的な建物で、広葉樹の可能性を発信するショールームならぬ、「ショーオフィス」。「森の端」という名前には、「森の中」と「まちなか」の境界にある場所という意味が込められています。
「広葉樹って針葉樹と比べて真っ直ぐな木が少なかったり、加工が難しいので、主要な建築材として使われてこなかったんです。でも僕らは用途の多様性を拡げるために、広葉樹であっても建材として使える可能性を示したかった。そこで、家具用に使われる薄くスライスした広葉樹の板材を複数組み合わせることで、板材を構造材で使える強度にまで高めることに挑戦しました」

ヒダクマは、創業当初からデジタルファブリケーションスタジオ、木工房、カフェ、宿泊施設が一体になった「FabCafe Hida」を運営。商品にならない「曲がり木」の広葉樹が持つ個性を活かした一点物の「作品」をクリエイターと共創したり、「曲がり木センター」では3Dテクノロジーを駆使して、規格外の木から建築・家具を設計し、加工まで一貫して行うことのできるサービスを実現するなど、主に木材サプライチェーンにおける「川下=家具製造」の領域で事業を展開してきました。
しかし、「森の端オフィス」は木工で使うような広葉樹の板材を建材にも活かすイノベーションを実現したことで、「川中=木材流通」にまで事業領域を拡大させることに成功したのです。
「『なぜ家具の会社が流通や建築まで?』と当初は疑問視されました」と、周囲から理解されづらかった当時の苦労を笑顔で振り返る岩岡さん。ビジネスのセオリーでいえば、市場がほとんどないとされていた広葉樹の建材にあえて挑戦することは、多くのビジネスパーソンの目には無謀や非合理にうつったことでしょう。それでも挑戦できたのは、規格化や効率化といった既存のビジネス論理から広葉樹という存在を拾い上げ、個性の価値化によって、新たな広葉樹の可能性を証明したいという、ヒダクマが創業時から灯し続けてきた思いがあったから。逆に言えば、既存のビジネス論理から外れているところにこそ、イノベーションの種は眠っていたのかもしれません。


「森を楽しむこと」から生まれた、「森をあそぶ」という新規事業
岩岡さんの運転で、次に向かったのは森の端オフィスから車で40分ほどの奥飛騨温泉のすぐそばにある、「道具番屋」という聞き慣れない名前の木造建築。建物のすぐ裏にはこんもりとした森が見えます。この森の所有者で、岐阜の駅前でテナントビル事業を営む新岐阜興業株式会社の代表・大橋司さんは笑顔で迎えてくれました。
「ここは何だと思います? 登山道に入り口があるように、森に入り口を作ろうということで、できたのがこの建物です。ここは、虫眼鏡や雪板といった森で遊ぶための道具を揃え、訪れた人が自然と森に関わることができる、いわば『森の入り口』。森の道具を貸出する管理人として僕らが『道具番』をするので、『道具番屋』という名前になりました」


この道具番屋もヒダクマがリサーチやコンセプト設計から携わっているプロジェクトの一つ。設計は先ほどの森の端オフィスと同じくツバメアーキテクツが行いました。
「元はこの森は、遊休林だったのです。せっかく先代が残した土地なのに、何十年も放置されたまま。このまま眠らせておくのはもったいないと思ったんです。そんなとき、ヒダクマのHPを見て、森の川上から川下まで一貫して関わっていて、広葉樹のこともすごく大切にしている、すごい会社だなと感じて」
と大橋さん。すぐに連絡を取り、一緒にプロジェクトに取り組むことになったと言います。
最初の取り組みは、森をひらき、多様な目線から森の可能性を探っていくリサーチワークショップ。温泉街や森の専門家、学生、企業人など多様なメンバーと共に、季節を変えて、数回にわたりワークショップを行います。対話を通じて、地域から出てきたのは「過度な開発はしてほしくない」、「宿にはしてほしくない」などといった声。その後も、遊び心を持ちながら、森の可能性を開いていくための企業研修、研究者のフィールドワークを重ねる中で大橋さんが大切にしたいと思ったのは「心地よさ」という身体感覚でした。
「私自身もこの森に入って、森の心地よさを実感しました。この森の気持ちよさを多くの人に知ってほしい。そう思った時、登山道の入り口のように、森を楽しむための入り口を自分たちでつくろうと」
その結果生まれたのが「道具番屋」という施設。森を開発するのではなく、「道具番屋」を設けることで、森で遊び、憩い、森の可能性を引き出す森林サービスでした。くしくも、大橋さんの本業である不動産テナント業と同じく、森という空間をユーザーに貸し出し、ユーザー(賃貸者)との共創で価値を生むという点において、道具番屋も似たビジネスモデルのように思えます。

森の心地よさを感じ、広げるための「開発しない開発」というコンセプトは、遊休林の収益化といった短期目線、計画的なビジネス発想からはきっと生まれ得なかったでしょう。大橋さんたちが大切にした「楽しさ」や「心地よさ」といった身体感覚は、通常のビジネスの世界では曖昧、主観的なものとされ、優先されることが少ないようにも思えます。
多様な目線を持ったステークホルダーに森をひらき、遊び心やワクワクを持って森の可能性を見つめ直すという、一見遠回りにも見える価値探求のプロセスを経たからこそ、曖昧で数字に置き換えられないけれど、たしかに実感できる価値を信じようという思いが芽生え、ユニークなコンセプトにつながったのかもしれません。

時間軸とビジネスの狭間で見つめ直す、ほんとうの持続可能性
奥飛騨温泉の「森の入り口」を後にして、私たちはさらに森の中へ。たどり着いたのは、広葉樹が伐採され、新たな若木が育ちつつある森でした。ヒダクマの代表取締役/COOで、トビムシの取締役でもある松本剛さんが森先案内人になって、飛騨の森の現在地を語ってくれました。
「これまでそのほとんどが家具にはならずチップ用として域外に流出していた飛騨の広葉樹ですが、地域の森林組合や製材所、木工作家等の連帯によって様々な取り組みが行われ、地域内外の協力社や顧客も増え、多様な活用がされるようになりました。最近では、チップ以外の用途、建築や家具になる用材率が約5%から20%にあがっています」

地域資源である広葉樹の価値化を創業時の目標の一つにしていたヒダクマにとって、これは喜ばしい大きな成果です。森の端オフィスや道具番屋といった、広葉樹の新たな可能性を切り開き続けていることの賜物のように思えます。一方で、いまヒダクマが新たに向き合っているのは、木材の利活用から、持続可能な森林との関わりへのシフトだと言います。
「単に森の木を伐って使うだけでなく、どのように森を再生し、次世代に引き継いでいくかという『森のライフサイクル』全体を見据えた取り組みがこれからは必要になってくるのではと考えているんです」
そこで、ヒダクマが始めたのは、森の持続可能性と森林産業の持続可能性の両方を追求するための「森の実験場」。たとえば、伐採後の森の更新可能性をどう高めるか、どのタイミングで次の伐採を行うべきか、といったテーマについて、大学や研究機関、民間企業と協働しながら実験的なプロジェクトに取り組もうとしています。
「『良い森』の定義ってすごく難しいんです。人間にとって良い森と、生き物たちにとって良い森は違うし、短期的なビジネス目線と100年単位で考えた時でも良い森は全然違ったものになります。そして、それは狙ってその通りできるものではない。」
例えば、今のマーケットニーズに応えて、売れそうな木を植林をしたものの、伐期する頃には売れる木のトレンドが変わってしまったり、ナラの木が売れるからと言ってナラだけを残していたら「ナラ枯れ病」のような特定の木がかかえる病気が蔓延し、育ててきた木が全滅してしまったり。需要サイドも、供給サイド側も変動リスクが多い森の経営は、一筋縄ではいきません。
「一つ言えることがあるとすれば、様々な変動リスクに適応するためにも、スギしか植えないといった画一的な森づくりをするよりも、なるべく様々な樹種が共生する多様性のある森を目指すしかないと考えているんです」

多様性は可能性。多様な選択肢を持ち続けることが最大のリスクヘッジになり、同時に利活用の幅が広がるという意味でも多様性はイノベーションの源だといえます。それはヒダクマの事業にも当てはまります。川下の家具製造から、川中の木材流通、川上の森林経営にまで事業領域を広げ、サプライチェーンを横断した取り組みを行うことは短期的にみれば非合理的な挑戦かもしれません。しかし、事業領域の多様性を高めながら、部分ではなく、森林というエコシステムを俯瞰し、その全体性の中で価値を生み出そうとすることは、長期的な目線で見れば理にかなっていると言えるかもしれません。
森をひらき、多様な価値を育むエコシステムを育む。「エコトーン」としてのヒダクマが果たす役割
川下から、川中、そして川上へ。森林業のサプライチェーンを辿るように森を巡ってきたツアーを終え、ヒダクマの原点であり、メイン拠点であるFabCafe Hidaに戻ってきました。7年ぶりにヒダクマ、そして飛騨の森を見たというエリさんはどんなことを感じたのでしょうか。
「『木の感じ』から、『森の感じ』に変わったなというのが一番に感じた変化です。創業時は素材としての木にどう付加価値をつけられるかを頑張ってきた。そのために、様々なクリエイターや技術を持った企業に森をひらいて、広葉樹の可能性を引き出し、一つずつ形にしてきた。そして今、その取り組みが奏功してきた中で、飛騨の森というエコシステム全体で価値をどのように生み出せるかという全体を捉える目線にシフトしているなあって」

領域は木から森に広がるけれど、変わらないこともありそうです。それは、これまでに何度も繰り返し出てきた「森をひらく」というキーワード。FabCafe Hidaの立ち上げから関わった岩岡さんはヒダクマらしさをこう解釈しました。
「いろいろやってきたけど、やっていることは全部同じだと思っているんです。経済合理性の視点からは見逃してしまう広葉樹が持っている価値を引き出して形にしたい。みんなが森に対して無関心になってしまうのが一番こわいこと。だから僕たちはFabCafe Hidaを作り、森の端オフィスを作り、道具番屋を作って、森の実験場も作った。森の新しい可能性をひらくために、僕たちは飛騨の森を開き続けてきた。そこは変わっていない。」

無関心から関心へ。飛騨の森から新たな価値を育んでいく、そのための「味方づくり」をすること。味方が増えるということは、森の新たな価値に気づき、築いていくための森への「見方」を増やすということでもあるのかもしれません。そして今、ヒダクマの創業から10年が経ち、 飛騨の森が持つ可能性を価値に変えるエコシステムが確かに立ち上がっているように感じられます。
その意味で、多様で分かりづらいとされるヒダクマの役割はエコシステムを育むための「エコトーン(汽水域)」なのかもしれません。陸と海の境界、草原と森の境界など、異なる環境や生態系の間に存在し、新たなエコシステムを育む場としての役割も果たすエコトーン。ヒダクマという存在自体が、森と人、林業者とクリエイター、ものづくりとテクノロジーといった異なる領域を混じり合わせ、木や森を生かしていくビジネスエコシステム生態系が育まれるエコトーンになっているのではないでしょうか。
そのようなヒダクマの役割をめぐる解釈を受け取ってエリさんは、ロフトワークのコアにある「運営の思想」を重ねます。
「ロフトワークが、立ち上げから関わって最近オープンした東海国立大学機構の共創拠点『ComoNe(コモネ)』があるじゃない?ここも、ヒダクマのように大学をひらいて社会との交わりを生む場所だけれど、そこで大切にしているのが、不確実性を排除し、効率性を高める『管理』ではなく、むしろ不確実性を歓迎して、その中にある未来の可能性をみんなで探求していく『運営』のアプローチなんだよね。答えや正解がわからないからこそ、面倒くさいし、こわいけれど不確実性を許容することからしか、イノベーションって生まれないのかなって」
「馬」の効率をどれだけ高めても「車」は発明されなかったように、イノベーションは計画性や効率性からは生まれません。新しい可能性を探索するあそび、余白、偶発性を許容しなければなりません。一方で、ビジネス活動である以上、確実性や収益性も求められます。ヒダクマもロフトワークも、そして多くの企業も、イノベーションに欠かせない偶発性とビジネスに求められる確実性の間で揺れ動きながら2つが両立できる道を探しているのかもしれません。
その新たな価値の探求プロセスのなかで、大切なのは、不確実性や答えのなさを面白がり、楽しむこと。「プロセスにこそ、豊かさがある」。ヒダクマの10年にわたる取り組みは、そんな価値観を思い出させてくれるような挑戦事例でした。
これからの10年、飛騨の森とヒダクマの未来にワクワクしている自分がいます。

執筆:北埜 航太
飛騨写真撮影:表 萌々花
ComoNe写真撮影:楠瀬 友将
【連載】最近気づいていないことは何か? ー多元世界探訪記
#01|伊藤光平(株式会社BIOTA 代表取締役)
見えない生き物たちの存在から未来を感じ取る
#02|平川克美(文筆家/「隣町珈琲」店主)
「株式会社」の起源と仕組みから、人口減少時代における企業の生き延びる道を考える
#03|ヒダクマが育む飛騨の森の共創エコシステム
森の価値を探求する「味方」を増やし、多様な「見方」から芽生えるイノベーション
#04|羽鳥達也(執行役員/設計監理部門・設計グループ代表)
人口減少時代の「動くインフラ」と“逆転の開発”
#05|津川 恵理(ALTEMY代表)
都市は〈滞在〉でおもしろくなる
Next Contents















